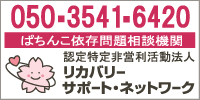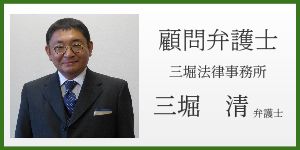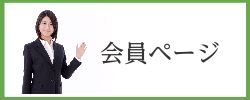プルタブを集めています。 御協力をお願いします。
プルタブを集めて車椅子を贈る運動を進めていますが、皆さんの日常生活で使用したアルミ缶のプルタブを集めると車椅子を贈ることができます。
皆さんが飲んだ後のアルミ缶のプルタブをカチカチとやって取って頂き、それを貯めて頂ければと思います。
捨てればゴミですが、集めれば役立てることができます。 貯めたものを事務局に持参して頂くか、送って頂ければ幸いです。
昨年は、22キロ集めることができました。 今後とも継続して行きたいと思いますので、御協力よろしくお願い致します。
安全・安心の街づくりのために
彩の国安全・安心事業協会
POWER VALUE SAVER
正規代理店

子ども虐待防止
オレンジリボン運動
当協会は、子ども虐待防止運動を積極的推進します。
従業員募集中
埼玉県内で当協会の会員企業が経営する景品買取所で働ける方を募集しています。
詳細は、当協会事務局まで連絡下さい。
一般社団法人 彩の国安全・安心事業協会
048(642)6638
支援団体紹介
当協会では社会貢献活動の一環として、毎年社会貢献団体に寄付金を贈呈させてもらっていますが、当協会が支援している団体の活動等につきましてご紹介したいと思います。
埼玉県心臓病の子どもを守る会

埼玉県心臓病の子どもを守る会の紹介
埼玉県心臓病の子どもを守る会は、1964年8月に発足しました。以来50年の長きにわたり、心臓病の子どもと保護者がよりよく人生を歩むために必要なことを学び合い、友情を育み、病児が自立に向けて歩めるようにと、さまざまなイベントを開催してきました。
現在、埼玉県内の会員は約230家族、県全体としての活動のほか、地域ごとに有志が集まって活動するなど、会員同士がより身近な関係を築きながら活動しています。
組織としては、(一社)全国心臓病の子どもを守る会の埼玉県支部で、全国には50の支部が心臓病児者の幸せのために手をつなぎ合って活動を行っています。内部組織には、15歳以上の患者本人の会「心臓病者友の会(心友会)」があります。
1年間の活動を紹介すると、春の総会(医療講演会も同時開催)に始まり、子ども同士・親同士の絆を深めるサマーキャンプ、新入会員の集い(相談会・講演会)、手品やゲームで子どもたちが大いに盛り上がるクリスマス会、親子みんなで料理を作って食べる手作り新年会など、毎回賑やかに楽しく活動しています。2016年11月には、結成50周年記念のクリスマス会を開催しました。お世話になった先生方をお招きし、100人を越える親子が参加し盛大にお祝いしました。
会では、先天性心臓病の最新医療や心臓病児者の社会福祉制度についての研修会を開くなどして会員同士の学び合いを深めています。50年前に比べると医療は格段に進歩し、今では生まれてすぐ心臓病で命を落とす子どもは少なくなりました。しかし、心臓病児が成長するとともにさまざまな問題も出てきます。学校に上がれば運動制限や親の付き添いの問題、就職するときにも病状を理解して無理なく長く働き続けられる職場はなかなか見つからないなどです。
会員同士が交流することで、悩みや心配なことを相談したり、不安を軽くすることができます。子どもたち自身も、病気を理解し、将来に向けて自分なりの自立の仕方を考えるようにもなります。さまざまなイベント開催の経費は、会員からの会費の他、県の補助金、共同募金、安全安心事業協会様などからいただく寄附などで賄っています。これまで守る会を支えてくださったみなさまへ感謝を申し上げるとともに、これからも心臓病児者の福祉増進へのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
公益財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

暴力団や薬物乱用のない「安全で安心な住みよい埼玉の実現」を目指して
公益財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター
専務理事 角屋 良夫
彩の国安全・安心事業協会様には、貴重な浄財を頂戴しておりありがとうございます。この紙面をお借りして心より御礼を申し上げます。
(公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターは平成元年5月1日「暴力及び薬物乱用のない安全で平穏なまちづくりに寄与する」目的で設立しました。
設立の経緯は、昭和63年9月、暴力団排除の気運が高まる中、薬物を使用した暴力団員が住宅街で拳銃を乱射し、市民が重軽傷を負ったうえ、現場に駆け付けた警察官が殉職するという凶悪重大事件が発生し、この事件を契機に県民の期待を受けてスタートしました。その後、暴力団対策法に基づき「暴力追放運動推進センター」として埼玉県公安委員会から指定を受け、又、住民の代理として暴力団組事務所使用差止請求等が行える「適格センター」として国家公安委員会の認定を受け、現在に至っています。
当センターの主な業務概要は、暴力追放・薬物乱用防止県民大会などの開催をはじめとする広報啓発活動や相談活動、暴力団被害者の保護及び救済活動、暴力団組事務所使用差止め訴訟、少年に対する暴力団の影響排除活動、暴力団から離脱しようとする人の援助活動などです。
<最近における暴力団排除活動及び薬物事犯の特徴>
最近の暴力団排除対策は、暴力団対策法をはじめ、政府から示された企業及び行政を対象とした暴力団排除の指針や暴力団排除条例などによりまして、組事務所使用差止め訴訟、暴力団離脱者の社会復帰支援など、全国的に様々な対策が進められています。加えて、裁判における判決結果も暴力団排除活動の追い風となっており、その結果、資金源の枯渇や暴力団構成員の減少が顕著となるなど、暴力団は相当なダメージを受けています。
しかしながら、依然として一定の勢力を保持しながら、「半グレ集団」などと手を結び、みかじめ料の徴収や振込め詐欺等の特殊詐欺事件を敢行するなど、組織の実態を巧みに隠し、企業や市民を装い様々な形態で不当要求行為を繰り返しており、社会の安全はいまだ脅かされています。
また、薬物事犯の検挙人員の半数以上は暴力団員であり、薬物事犯が暴力団の資金源になっている状況が窺えます。加えて、大麻の栽培プラントが相次いで摘発されているほか、大麻事犯が若年層へ拡散しているという特徴が認められ、大変憂慮される状況です。
このような情勢の中、当センターとしましては、暴力団の存在を許さない、そして薬物乱用を根絶するという社会環境づくりのための活動を継続して推進してまいりますので、これからも、皆様のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
一般社団法人 埼玉県障害難病団体協議会
難病児者を取り巻く諸課題について
この度は、彩の国安全・安心事業会様よりご寄付をいただきまして誠に有り難うございます。これもひとえに私ども「障難協」の活動を平素よりご理解いただいていることに感謝するとともに、身にあまる光栄に存じます。
私ども埼玉県障害難病団体協議会「障難協」は、「埼玉県内の障害児者、難病児者及びこれらの家庭の援護を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする」として、昭和48年(1973年)2月4日に設立され、現在はベーチェット病友の会埼玉支部や埼玉県腎炎・ネフローゼ児を守る会など24団体が加盟し、本人や家族の悩みや不安を少しでも解消できるように情報提供や知識を深める活動をしております。
平成25年に施行された「障害者総合支援法」によって、医療のみならず、福祉の分野でも各種サービスが受けられるような制度に変わりました。しかしながら、行政機関及び関係団体との連携を含めて、制度の主旨と理解が浸透しておらず、制度が十分に活用されていないのではと危惧しております。今後は、関係する組織と一層の連携の強化を図り、関係者の資質向上への支援策等も重要ではないかと思っております。
また、難病患者が「障害者の範囲」の定義の中に組み込まれましたが、就労につきましては「障害者雇用促進法」の中の障害者雇用率として算定されない難病患者(障害者手帳を持たない、持てない人)が多く、就労チャンスは依然厳しい状況下にあります。
*障害者雇用率制度:企業には全労働者の2.2%の障害者を雇用する法的義務があります。その対象となる障害者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する、身体、知的、精神障害者です。
しかしながら、掛かる状況下で、県庁関係各課及び関係する団体と「難病患者の就労支援について」精力的に話合いを進めております。そう遠くない時期に具体的な支援拡充体制が整うものと期待しております。
私ども障難協は「ノーマライゼーション」の理念を信じて、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しながら、地域の中で共に手を取りあって暮らすことのできる社会にこれからも尽力して行きますので、どうか皆様には引続き、より一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げます。
◆【法定雇用率】とは
法定雇用率は5年ごとに算定し、見直すことになっている。平成30年4月1日から精神障害者を算定基礎に追加された。企業・団体別の法定雇用率は以下のとおりです。
・民間企業 ・・・2.2%(対象労働者45.5人以上の規模)
・特殊法人・独立行政法人・・・2.5%(対象労働者数40人以上の規模)
・国・地方公共団体 ・・・2.5%(除外職員除く職員数40人以上の機関)
・都道府県等の教育委員会・・・2.4%(除外職員除く職員数42人以上の機関)
※平成33年4月より前に、さらに0.1%ずつの引き上げが予定されている。
一般社団法人 埼玉県障害難病団体協議会 代表理事 鍜治屋勇


認定非営利活動法人 みんなの夢の音楽隊
「みんなの夢の音楽隊」とは、ひとりひとりが自分らしく生きていくことを応援する仲間たちの「つながり」のことです。子どもも大人も、障害のあるなし、国籍を問わず、だれもがみんなで楽しく暮らしていけるように、日頃の生活や自分の悩み事、社会や地域の問題を語り合い、よりよい人間関係、地域づくりを目指しています。
この1年で、いくつか新しい活動を開始しました。さいたま市の小学校体育館を借りた子どもの居場所づくりと、事務所1Fでの子ども食堂は定期的な活動です。会を重ねるごとに参加者が増え、体育館の居場所づくり活動には毎回30~50人の子どもたちが参加しています。
子ども食堂は、大きく宣伝などはせず、静かに運営しています。お友達同士でも、気軽に一緒にご飯を食べられる会として、毎回10人に満たないくらいの少人数での開催を目指しています。今後も、たくさんの子どもを呼ぶのではなく、子ども食堂の数を増やし、近隣で数カ所開催できるようにしていく予定です。
さらに、10月からは近隣公民館の和室を借り、競技かるたのサークル活動を始めました。全国大会に出場するなど、子どものやりたい気持ちを後押ししながら楽しく活動しています。
11月には、さいたま市の事業「こどもがつくるまちミニ南区」をNPO法人子ども劇場おやこ劇場埼玉センターと共同で開催しました。お店屋さんづくりから始まりましたが、銀行や行政の役割を作っていくうちに、「税金が必要だ」と、子どもたちが気付きます。ですが、その認識を全員で共有するのは難しく、大変な議論に発展しました。最後はリーダーの子どもが、頭を下げて税金への理解を求め、他の参加者はアルバイトの時給アップの要望と引き換えに税金への協力を同意するなど、大人がびっくりするような子どもたちの姿を見ることができました。
「さいたまトリエンナーレ2016」では、ボランティアエキストラとしてゾンビメイクをして東武伊勢崎線の車内でパフォーマンスをしました。最初はメイクに戸惑う様子もありましたが、本番では役者顔負けの素早い衣装替えやメイクアップをこなし、来場されたお客様を驚かせていました。
12月には、アフガニスタンから新しいカルチャーセンター建設についての報告があり、クラウドファンディングを使って17,500ドル(約200万円)の支援を世界中から集めることができました。日本からも5,000ドル(約60万円)を送金しました。
盛りだくさんの1年間を終えて、2017年も、子ども食堂の活動を継続し、ミニ南区だけでなく、ミニ中央区、ミニ西区も開催します。
5月にはフィリピンの女性の自立を支援するNGO劇団「あけぼの」の日本公演を開催し、愛知、京都、大阪、千葉、川崎、埼玉、長野の公演をみんなの夢の音楽隊でサポートしました。その傍らで、来日した劇団メンバーの父親を探すという目的もあり、大人が奔走しました。帰国直前の空港で面会が実現するなどし、ひとりひとりの子どもが、心から喜べる手助けができたのではないかと思いました。
すべての活動に通じているのは、Making Children Laugh is a Goal!(子どもたちを笑わせよう!)という気持ちです。子どもと一緒におなかを抱えて大笑いしてしまうような、そんな世界を創っていきたいです。みなさまのご支援・応援を、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
認定NPO法人 みんなの夢の音楽隊 理事長 今川夏如


社会福祉法人 雀幸園
子どもたちが幸せに飛び立つように
社会福祉法人 雀幸園 理事長兼園長 新木 弘子
雀幸園は昭和53年7月に現理事長の父、深田正光初代理事長が埼玉県熊谷市に入所定員60名の児童養護施設を開園しました。
深田氏は昭和23年から戦争孤児たちの里親になり、我が家では男の子ばかり17人を育てていました。名前の違う子が家にたくさんいて、当時一緒に住んでいた私(新木ひろ子)は「お姉さん」と呼ばれるのが嫌で、「何でよその子まで」と反抗していた時期もありました。また、深田氏は終戦前夜、知覧から最後に見送った若い特攻隊員が母親や恋人の写真を胸に抱いていた姿が忘れられないと言っていました。その償いから戦争孤児を里親として預かっていたのかもしれません。
やがて深田氏は財産をすべて売り払い、この施設を作りました。雀を子どもたちに例え、幸せに飛び立つことができるように「雀幸園」と名付けた深田氏は開園した翌年に亡くなりました。今でこそ児童福祉が認知されていますが、開園当初は「人様の子どもを預かって何をするのか」と冷たい世間の目、壁がありました。万引きするのではないか、水も流すな、残飯を捨てるなと言われながら、両親が頭を下げ、地域住民に理解を求める姿を今でも鮮やかに覚えています。
当園は現在79名の子どもたちが生活しています。その中で虐待(身体的、心理的、性的、ネグレクト)を受けた子どもは45%に達しており、育児放棄や親の精神疾患で十分な養育を受けられない子どもを含めると70%に上ります。施設は子どもたちの生活の場であり、出来る限り家庭に近い、落ち着いた雰囲気の中で生活できるように心を配っています。子どもたちは施設から通学していますが、それ以外に余暇や趣味を楽しみ、四季折々の行事や子ども会活動を通して健全に成長し、社会的に自立するための支援がなされています。
子供たちが生活する施設には様々な形がありますが、1つの施設の中でも少人数のグループに分かれ、より家庭に近いスタイルで生活する施設や、地域の中で生活する地域小規模施設やグループホームなども増えています。当法人でも本体施設の他、3つの地域小規模施設とファミリーホームの事業を行っており、地域貢献として子育てサロンやショートステイ事業を展開しています。
本年も雀幸園に対するご理解ご支援を心からお願い申し上げます。